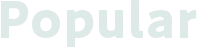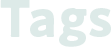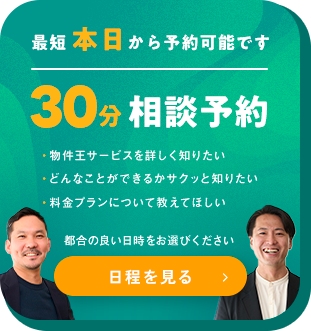目次
まえがき
一年もあっという間に終わり、社会人としての2年目に突入しました。
今回は3月の出来事のお話なので、一年目としての最後のお話になります。
そしてこのオウンドメディアの最後になります。色々書きたいことやかけることはあるのですが、もう新人ではなくなったので。
ということで、最後に相応しいか分かりませんが行ってみましょう。
課題作成のお話
前回お話ししていた課題の作成のお話です。
簡単におさらいすると、「元々のプロトの仕様に問題があった」という話ですね。
物件種別の管理に問題があったため、それを解決するコードの実装課題です。
詳細な課題内容などはここでは省き、作ってみての所感などをお話します。
初めての課題作成をしてみて
今までのメンテナンス課題などの日々の業務での課題は作成されたものを割り振られて対応していっているわけです。コーダーなので作業者ですから、内容を読み込んで対応していく流れですよね。
ですが今回は自分がその課題を制作するというわけで、色々迷いました。
課題作成に必要な要素はざっと以下のような感じです。
- ・課題のタイトル
一目見てどんな課題の大枠かを読み取る事ができるもの。 - ・具体的な課題の内容
どんな対応が必要で、その詳細についてを記すもの。 - ・課題を作成した経緯
なぜこの対応が必要なのかやどこで発見された問題なのか。
これらにプラスして参考資料などを貼付するような流れです。
これらを記述していて苦労したのは「一言でどう言い表すか」ということと「文章をどう簡潔に伝わり切るように構成するか」でした。
一言でどう言い表すか
課題のタイトルなどに設けるものですが、これが意外と難しい。
例えばこのオウンドメディアの課題とかだと「3月の出来事をオウンドメディアの記事にまとめる」という感じになりますね。なんか簡単に思えますが、これが課題によって変わってきます。
複雑に実装するコードがある場合や、結局このコーディングで何をしたいのかというのを言い切らないといけないからです。
なので「ここのコードが好ましくないからこういう風に変えたくて、でそれを実装するとこう変わるからつまり...」みたいな感じで頭の中で考えていることを、一言でパッと言い切ろうとする時にグルグル考えちゃいました。
また、適切な用語を絞り出すのも難しく、「〇〇の実装」とかにしてみたけど8割はあってるけど少しニュアンスが違うな...みたいなことになりがちでした。
いかに文章を簡潔に、伝わり切るように構成するか
これも先ほどの話題と地続きな話ですが、対応する作業内容を文章で理解できるように簡潔にする、ということです。
対応する作業内容をそのまま文章にしてみるとします。
なんとなくの想像でわかる方もいるかと思いますが、ややこしくなりますよね。
対応作業のおおまかなものを想像しやすくさせるための文章になるわけで、全部を説明するわけではない、ということを意識しないといけません。
ですが、簡潔すぎると説明が不十分すぎて必要な対応ができないままになってしまったりします。
だらだら〜と書いてしまわぬようにしつつ、必要な説明を抜け落ちが無いように文章を構成するのです。
具体的な課題をお話しできないため、ちょっと想像しづらい内容だったかもですが、結論何が大変だったかというと「いい塩梅でわかりやすくまとめ切る」ということでした。
こういう要素は日常会話とかでも結構大切ですよね。
ず〜っとだらだら話すと聴く側も疲れますし、簡潔すぎると「結局何を伝えたいの?」と疑問が残ってしまったりしますから。
"まとめる"というスキルは簡単じゃないということですね。
仕様書作成のお話
新しい課題で、「仕様書の作成」というものが舞い込んできました。
今回は、社内で使うツールの作成にあたっての仕様書になります。
ツール自体は「社員の勤怠状態を把握しやすくするもの」として作成されます。
もっと簡単にいうと「いつ誰が休んでて誰が稼働しているのか」を把握しやすくするものです。
仕様書と聞いてピンとこない人も多いと思うので少し仕様書についてお話します。
仕様書とは?
仕様書(しようしょ)とは、システム・ソフトウェア・製品などを作るために必要な内容やルールをまとめた文書のことです。
簡単に言えば、「これをこういうルール・やり方で作ります」という設計図みたいなものです。
- ・👨💻 開発者:どう作るかを理解するため
- ・🎨 デザイナー:どんな画面や動作になるかを把握するため
- ・🧪 テスター:正しく動くかチェックする基準にするため
- ・💬 クライアントや関係者:最終的にどうなるのか共通認識を持つため
人それぞれによって用途や捉え方も少し変化するものですが、一貫しているのは「誰が見ても何の仕様書なのか理解できる」ものとして作成されるということです。
作成してみての所感
仕様書はブラッシュアップしようと思えばいくらでもブラッシュアップできてしまうもので、「完成した!」と声高々にいうことはまだできていませんが、現状の所感をお話します。
"とにかく難しい"という一言に尽きました。
今、オウンドメディアなどで書いている文章は今まで学校などで培ってきたスキルを無意識的にも活かして記述しているわけですが、仕様書に関しては書き方が全く違ってきます。
その点で言えば先ほどの課題作成の文章とも異なってくるわけです。
順序的に言えば、
【課題を見て全体を把握する▶︎仕様書を見て詳細な内容を把握する▶︎作業する】
という大まかな流れになるはずです。
なので課題を見て「で、実際どんな感じなんや?」となる部分などが集約されているものになるので、必要事項を網羅している必要があります。
れらを考案してまとめて、文章的にも理解しやすく簡潔にして...というふうに作っていったのです。その作業が大変でした。
バーっと書いていくのはできるんですが、それを整理する作業が迷いに迷ったりして、「この内容はこのセクションでいいのか?」と自問自答していました。
また、5W1Hの要素を盛り込むことも大切で、それらを抑えることでこの仕様書の質も上がるのです。
5W1Hというのは
- ・When(いつ)
- ・Where(どこで)
- ・Who(誰が)
- ・What(何を)
- ・Why(なぜ)
- ・How(どうやって)
というやつです。
これらを抑えることで、よりツールなどの制作意図やそれを制作してどんなアドバンテージが生まれるのかや工数を割く価値があるのかの再確認などにも使えます。
これらも考えながら文章を作成していくのはやりがいとか学びはたくさんありましたが、とにかく悩みに悩んだり四苦八苦しました。
文章を作成するということってそれくらい難易度の高いことなんだなって改めて思いましたね。
小学生の頃から何かと書かされてきて「めんどくさ〜い」と嘆きがちでしたが、ここにきて何でそのカリキュラムが組まれているのかが見えてきましたね。
この仕様書のお話についてはまた進展などがあればお話していきますm(_ _)m
新しい仲間のお話
ここまで業務のお話をしてきましたが、春から仲間になる新人さんのお話をしておこうと思います。
今回は残念ながら僕の所属しているチームに新しい仲間は来ませんでしたが、他部署に入った新入社員の方のお話です。
パーソナルな部分とかはここでは割愛するので、僕の感じたことをお話をしていくのですが、まずとんでもなくポテンシャルの高い方だと感じました。
なんとバンドマンで映像制作とかにも精通しているという非常に物件王らしい方で、実は以前からインターンシップもあったので、時々会社では会っていました。そこでコミュニケーションしていて、コミュニケーションの上手な方だなと感じていました。
入社前のインターンシップで少し業務をされていて、その振り返り的なプレゼンをしていただいたのですが、それも昨年自分たちが行ったものよりもいいものだったなと感じました。
とにかく目標も高く持っていて、向上心の塊のように見えましたね。
個人的にコミュニケーションした際も年も近いためか、話しやすくて趣味もしっかりやりこんでいてとても好印象でした。
映像制作経験もあるというところでは自分とも重なる部分も多く、なんだかこれから仲良くしていければなと思ったりしています。
特に良かったなと思ったのは「笑顔でしっかりお話しできること」だと感じました。
すごく当たり前のようなことなんですが意外とこれができる人って少ないし難しいと思うんです。
どうしてもちょっとわざとらしく引きつっちゃったりしてしまいますよね。自分がすごく苦手な分野なのでより彼がすごいなと感じます。
そのコミュニケーション能力はきっと業務やそれ以外の部分でも部分でも活きてくると思いますし、それに助けられる日も近いかもしれませんね。
そんな高ポテンシャル人間の参戦でますます物件王が成長していくと思うのでそんな未来が少し楽しみになりつつ自分も負けずにオウンドメディア然り、日々の業務然り、そして個人の活動も頑張っていきます💪
最近の業務のお話
さて、色々とお話しした最後に一年経ってみてのお話をできればと思います。
新卒一年目のひよっこエンジニアとしてスタートしたわけですが、この一年でいろんな変化がありました。オウンドメディアが始まったり、仕様書の作成なんていう少しハードルの高いものも任されたりといろんな経験を積むことができました。
メンターの方と共に歩みを進めていき、いろんなフィードバックももらった一年でした。
お陰様で、今ではメンテナンス業務も以前より任せてもらえるようになったり、コーディング以外の業務も増えたりと頑張っております。
そんな中で最近やっていることを少しお話しします。
学びを得ていること
僕の担当している業務ではないのですが、毎週ミーティングして進めている業務があり、それについてのフィードバックがチャットで飛び交っている最近です。そのやりとりなどを見て学びを得るようにしています。
...と言っても難しい内容でもあるので、学びを定着できている自信はないのですが、とりあえずやりとりなどを読み込むようにはしています。
先輩たちも人間なのでミスすることや、好ましくない対応になってしまったりすることもあります。その出来事で当人は「改善していこう」と改めることができますが、どうしても外野の人間などは見送りがちで同じようなミスをおかしがちだと思います。
なので、もし同じようなミスをしてしまった時は、うまくリカバリーできるように学びを止めないようにしています。
「人の振り見て我が振り直せ」という言葉を常日頃から意識して行動を改めたりしていくと人間としても成長できると思うので、続けていきたいですね。
あとは、自分の成長したところだと思っていることですが、コミュニケーションに関しては常に向上している気がしています。
ミーティングなどで話す時に「なんか今日うまく喋れたな」とか「もっとこう話そう」とか自分自身でフィードバックするようになってきたんですよね。
個人的には自分のことを口下手だと思っていて、なかなか上手にできないなって思うことが多くあるのですが、そんな自分でも毎日取り組んでいくことで、自信も実力も少しずつ付いてきました。
こういう目に見えずらいスキルこそ、塵も積もればって言われるものだと思うので、みなさんも日常での細かいところから少しずつ見直していくのはとても良いことなんじゃないでしょうか。
あとがき
以上が3月号でした。
春は出会いと別れの季節ってよく言われるので皆さんもそんな経験があったかもしれませんね。
このオウンドメディアもここで終わってしまうようですが、どこかでまた会えることを楽しみにしています。
一年間...と言っても途中から始まったので連載期間的には半年ほどでしょうか。お付き合いいただきありがとうございました。
基本みんな同じ空の下で生きているので離れ離れになったりしても二人三脚な心積もりで頑張っていきましょう。
あとは花粉を撃退しましょう。